害獣駆除にかかわる法律とは?罰則の内容や対象となる動物について
公開日:2025.4.9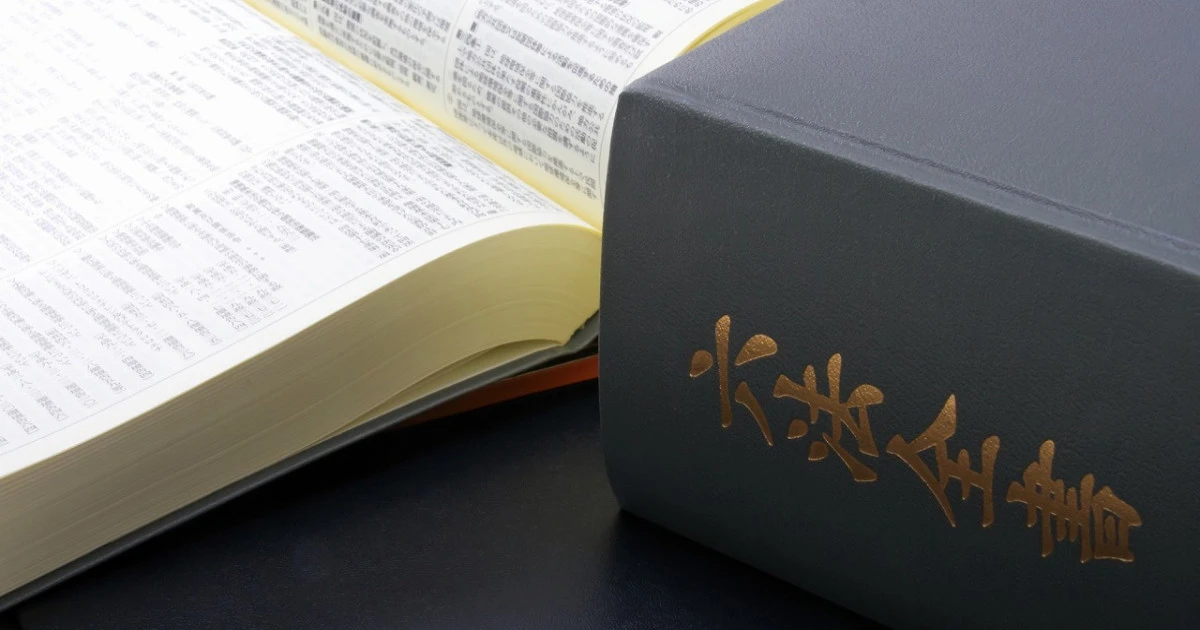
近年、人間や自然環境を取り巻く状況の変化により、さまざまな害獣が人里に出没するようになっています。しかし、これらの害獣は法律によって、勝手に駆除することが禁じられています。
今回は、害獣駆除に関わる法律や、対象となる動物について解説します。
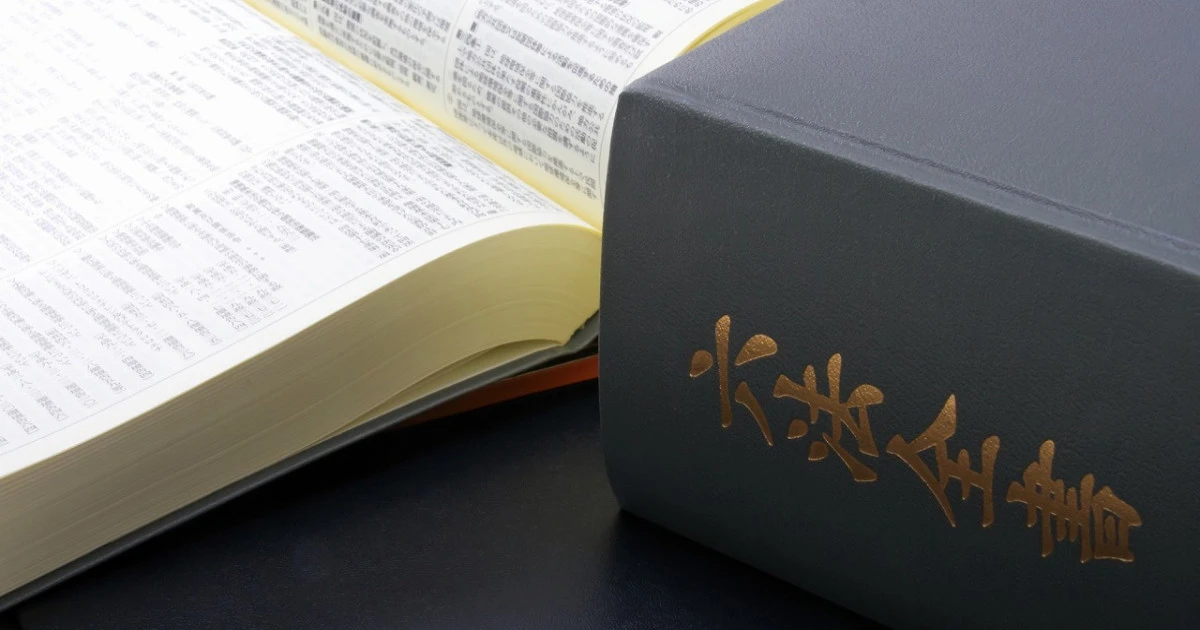
近年、人間や自然環境を取り巻く状況の変化により、さまざまな害獣が人里に出没するようになっています。しかし、これらの害獣は法律によって、勝手に駆除することが禁じられています。
今回は、害獣駆除に関わる法律や、対象となる動物について解説します。


害獣とは、農村部で作物を荒らしたり、民家に住み着いて被害を与えたりする動物のことを指します。ただし、これらの動物たちは本来、人間の生活圏とは離れた自然環境で暮らしている生き物です。
そのため、こうした害獣の駆除には法律による規制が設けられています。
日本では、害獣駆除を規制する法律として「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(通称:鳥獣保護管理法)」と「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(通称:外来生物法)」の2つがあります。
鳥獣保護管理法は、国内に生息する野生鳥獣を保護・管理することを目的とし、個人がむやみに捕獲や狩猟を行うことを禁じています。
ただし、すべての野生動物が一律に保護されているわけではなく、一部の動物については狩猟が可能とされています。
そのため、ネズミやモグラなど、環境衛生に悪影響を及ぼす動物は対象外とされています。
野生鳥獣を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づき自治体などに申請し、許可を得る必要があります。なお、申請から許可までに時間がかかることもあるため、余裕をもって手続きすることが大切です。
鳥獣保護管理法に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
たとえば、無許可で野生鳥獣を捕獲したり、定められた方法以外で狩猟を行ったりすると処罰の対象となります。
一方、外来生物法は、日本国内の生態系や人の生命・身体、農林水産業などに被害を及ぼすおそれのある外来種の飼養、輸入、放出などを規制する法律です。
この法律により、特定外来生物に指定された生き物を無許可で捕獲・輸入・飼養することが厳しく制限されています。野生生物を個人がむやみに取り扱うことのないよう、管理体制が整えられています。
外来生物法に違反した場合には、個人であっても最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があり、法人の場合は最大で1億円以下の罰金が課されることもあります。
違法な輸入や飼育、放出などは重大な法令違反となるため、十分な注意が必要です。

前述の通り、日本には法律により個人が勝手に駆除してはいけない害獣が多数存在します。以下に、保護対象となっている主な生き物の例を紹介します。
・ハクビシン
全国各地で確認されている中型哺乳類で、鳥獣保護管理法の対象となっています。屋根裏や天井裏に住み着き、糞尿による悪臭や建材の腐食などの被害が出ることがあります。
顔の中央に白い線があるのが特徴で、夜行性のため発見が遅れがちです。
・アライグマ
「特定外来生物」に指定されており、現在ではほぼ全国に分布しています。屋根裏などに住み着き、糞尿による汚損や悪臭などの被害をもたらしています。
・タヌキ
全国的に分布しており、人里や市街地にも出没することがある哺乳類です。
雑食性で、生ごみをあさったり、畑を荒らしたりするほか、民家の床下などに住み着いてしまうケースもあります。鳥獣保護管理法により保護されているため、駆除には必ず自治体の許可が必要です。
・アナグマ
本州を中心に広い地域に生息する害獣です。その名の通り、穴を掘って住処を作る習性があり、市街地では床下に住み着くこともあります。
また、近隣の生ごみや農作物を荒らすといった被害も報告されています。
・チョウセンイタチ
西日本を中心に生息する外来生物です。民家に侵入し、建材に穴を開けるなどの被害が発生しています。
・コウモリ
一部のコウモリは鳥獣保護管理法の対象で、無許可での駆除や捕獲はできません。屋根裏や換気口に侵入し、糞害や衛生面での問題を引き起こすことがあります。
また、人に直接触れることで病原体を媒介するリスクもあるため、慎重な対応が必要です。
・ムクドリ
北海道から沖縄まで全国で目撃される鳥で、群れで行動する習性があります。
大量の糞や羽毛による被害があるほか、夕方には鳴き声が騒音となり、周辺住民に迷惑をかけることもあります。一度追い払っても、再び同じ場所に戻ってくることがあるため、対策が難しいとされています。

鳥獣保護管理法では、野生動物の駆除作業を行う場合、あらかじめお住まいの自治体に捕獲許可を申請する必要があります。
さらに、個人で捕獲を行うには、所定の免許を取得していることが条件となります。
害獣駆除を目的とした主な免許には、以下のような種類があります。
・網猟免許(網を使った捕獲)
・わな猟免許(罠を使った捕獲)
・第一種銃猟免許(散弾銃やライフル銃などを用いた駆除)
・第二種銃猟免許(空気銃を用いた駆除)
これらの免許は、受験資格を満たした上で、適性試験や技能試験などに合格することで取得できます。
また、多くの自治体では害獣駆除が許可される時期(猟期)を定めており、それ以外の期間に駆除を行うことは原則として認められていません。
免許には有効期限があり、狩猟を行う際には、毎年度、狩猟を希望する都道府県に申請し登録を行う必要があります。
この免許は、満20歳以上の日本国民であれば取得可能ですが、一定の条件に該当する場合には取得できないこともあるため、詳しくは各都道府県の担当窓口に確認することをおすすめします。
なお、農作物を守るために電気柵などを設置して害獣の侵入を防ぐといった対策を講じる場合には、免許は不要です。

このように、野生動物は法律によって駆除が厳しく制限されています。
しかし、そのような野生動物への対処を安心して任せられるのが、害獣駆除業者です。
専門業者をおすすめする理由は、以下の通りです。
・鳥獣保護法に抵触しなくて済む
素人が対策を試みると、誤って野生動物を傷つけてしまい、鳥獣保護管理法に違反して罰則を受ける可能性があります。
その点、業者は行政の認可を受けており、法令に則った方法で安全に駆除を行ってくれます。
・安全に駆除してくれる
野生動物は感染症やアレルギーの原因になる場合があり、駆除には危険が伴います。
業者には専門知識を持つスタッフが在籍しており、適切かつ安全に対応してくれます。
・必要な手間を省ける
駆除や予防を自分で行うには、道具の準備や作業の段取りなど、何かと手間がかかります。業者であれば電話一本で迅速に駆けつけてくれるため、面倒な準備や作業を自分で行う必要がありません。
とくに忙しい方にとっては、予防策まで含めて任せられる点が大きな魅力です。
・アフターフォローも万全
多くの業者では、再発時のアフターフォローを用意しています。
保証期間内であれば無料で再駆除に対応してくれるケースもあるため、事前に保証内容を確認しておくと安心です。
必要な手続きや安全面の配慮、そして再発防止まで対応してくれる専門業者の存在は非常に心強いものです。
害獣による被害でお困りの際は、まずはお住まいの地域の対応業者に相談してみましょう。

法律で保護されている害獣の駆除を業者に依頼する際、気になるのがその費用です。
駆除作業から再発予防までを含めたトータルの費用相場は、約10,000〜45,000円程度とされています。
ただし、これはあくまでも目安であり、現場の状況や駆除方法、対象の動物によって価格は変動します。
少しでも費用を抑えるためのポイントとして、以下のような方法があります。
・複数業者から見積もりを取る
最低でも3社以上の見積もりを比較することで、料金の相場やサービス内容を把握しやすくなります。
電話やメールで簡易的な見積もりを出してくれる業者もありますが、現地調査を依頼することで、より正確な見積もりが可能です。
また、見積もりを比較する際は金額だけでなく、作業内容の詳細まで確認することが大切です。
費用が安く見えても、消毒や再発防止処理などが含まれていないケースもあるため、注意しましょう。
・割引キャンペーンを活用する
業者によっては、期間限定の割引や、インターネット申込限定の特別料金を実施していることがあります。
こうしたキャンペーンを上手に活用することで、同じ内容でもよりお得に依頼できる可能性があります。
お住まいの地域で対応可能な業者を検索し、割引や特典の有無も含めて比較検討してみましょう。
このように、費用を抑えつつも安心して駆除を任せるためには、業者選びと事前の情報収集が非常に重要です。
無理に安さを追求するのではなく、サービスの質と総合的なコストパフォーマンスを見極めることが、失敗しないコツといえるでしょう。
